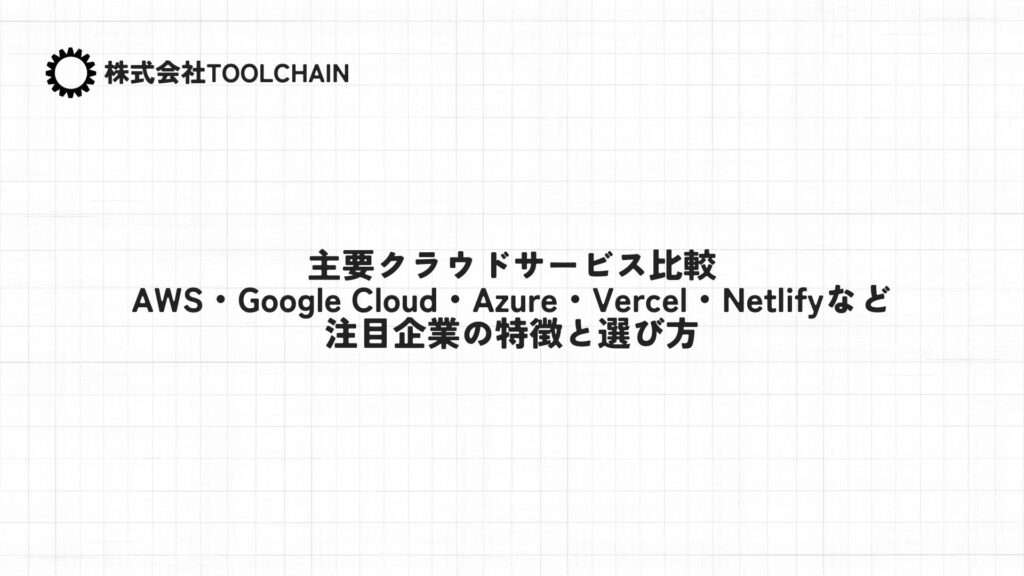
【2025年版】主要クラウドサービス比較:AWS・Google Cloud・Azure・Vercel・Netlifyなど注目企業の特徴と選び方
2025年1月6日 |
Research
はじめに
クラウドサービス市場は今や成熟期に入り、大手ベンダーから特化型の新興プレイヤーまで、多様な選択肢が存在しています。本記事では、AWS・Google Cloud・Azureの三大クラウドに加え、Vercel・Netlify・Cloudflareなどの注目企業について、強み・課題を比較し、導入検討の参考となるポイントをまとめます。
大手クラウドベンダーの強みと課題
AWS(Amazon Web Services)
- 強み: Lambda を中心とした Serverless構成の柔軟性。
- API Gateway、DynamoDBとの統合もスムーズで、マイクロサービスアーキテクチャに適している。
- 課題: 類似するサービスが多数存在し、習得コストが高い(例:Aurora、RDS、DynamoDB などのDB製品群)。
Google Cloud Platform(GCP)
- 強み: Cloud FunctionsとGKEによるServerless + コンテナのハイブリッド構成が容易。
- Gemini(最新AIモデル)の社内導入を推進し、AI領域への先進的な取り組みが進行中。
- 課題: 他社に比べ、エンタープライズ支援体制の整備は途上と感じられる。
Microsoft Azure
課題: 機能の重複やUIの複雑さから、初学者にはとっつきにくい面も。
強み: Azure Learn など 学習コンテンツが充実。
特に大企業向けの技術支援やSLA保証、MS製品との統合が強い。
特化型クラウド:Vercel・Netlifyの戦略
Vercel
- Next.jsの開発元として、Reactエコシステムとの統合が非常に強力。
- Webアプリ開発に特化し、開発からデプロイまでの体験が洗練されている。
Netlify
- Jamstack構成に最適化された シンプルで高速なデプロイ環境。
- Platform Engineering に注力し、企業内DX支援ツールとしても評価が高い。
その他のクラウドベンダー・挑戦者たち
Cloudflare
- CDNを軸に成長し、Serverless Workersによるエッジコンピューティングにも注力。
- 2025年にはコンテナ管理機能の提供も予定されており、クラウド基盤としての領域を拡大中。
Red Hat(OpenShift)
- マルチクラウド対応のKubernetes基盤。
- AWSやGCPなどの特定ベンダー固有機能とは連携しづらいため、エンタープライズ向け構成に適した選択肢。
Salesforce(Heroku)
- PaaSの草分け的存在で、Gitベースの簡易デプロイが特徴。
- 近年はメンテナンスの停滞やSalesforce製品との統合の乏しさから、評価が分かれる。
ニッチプレイヤーの可能性
Platform.sh
- Symfonyの共同制作者がCPOを務める、Webアプリ特化型のPaaS。
- Renderの代替として比較されることが多く、ヨーロッパ市場での存在感を拡大中。
Mia-Platform
- イタリア発、Git連携 + シンプルUIによる低学習コストが強み。
- 中小規模プロジェクト向けの選択肢として注目される。
Huawei Cloud
- 中国市場を中心に、OSS貢献(Apache ServiceCombなど)を進める。
- 海外展開では政治的リスクも存在するが、政府・公共機関向けに導入されるケースも。
日本市場の視点と今後の展望
国内では、富士通・NECといった独自クラウドサービスも存在しますが、国際的な技術競争力やスケーラビリティではまだ差があると感じられます。
今後は以下の点に注目すべきでしょう:
- 大手クラウドの進化(AI・Serverless・セキュリティ)
- 特化型クラウドの使い分け(例:Vercel × Webアプリ、Cloudflare × エッジ)
- 定期的なベンダー比較・レポート作成の重要性
まとめ:最適なクラウド選定のために
クラウドサービス選定においては、「最大公約数的な選択」ではなく、プロジェクトごとの目的・スケーラビリティ・チームスキルに応じたベストマッチの選定が必要です。
弊社としても、最新動向を定期的にキャッチアップし、プロダクト開発に最適なクラウド選定ガイドとして、今後も情報発信を継続していきます。