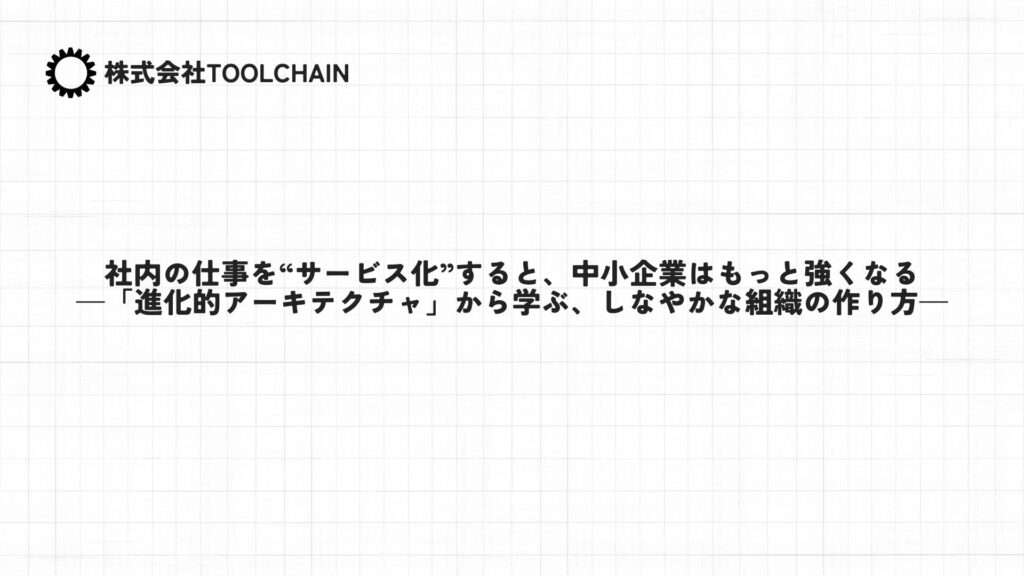
社内の仕事を“サービス化”すると、中小企業はもっと強くなる—「進化的アーキテクチャ」から学ぶ、しなやかな組織の作り方—
人手不足の時代、どうやって組織を強くするか?
「人手が足りない」「引き継ぎがうまくいかない」「あの人が辞めたら回らない」
多くの中小企業が直面しているこれらの課題は、組織の柔軟性や“見える化”ができていないことに根本原因があります。
先日読んだ『進化的アーキテクチャ(Building Evolutionary Architectures)』という書籍の中に、こうした問題を解決するヒントがありました。
大企業向けの技術書のように見えますが、実は中小企業にこそ活かせる考え方が詰まっていると感じたので、今回はそのエッセンスと、中小企業にとっての実践的な応用方法を紹介したいと思います。
「進化的アーキテクチャ」とは?
一言でいうと、「変化に強く、継続的に改善できるシステムや組織の設計思想」です。
ポイントは以下の3つです:
- 適応度関数(Fitness Function) 組織やシステムが「うまく動いているかどうか」を測るための数値やテスト。例:サービスの利用率、レスポンスタイム、顧客満足度など。
- モジュール化(Modularity)システムや組織を、役割ごとに分離し、独立して改善・交換できるようにする。
- Conwayの法則との連動 「組織構造は、そのままシステム構造に現れる」という考え。つまり、組織の分け方と仕事のやり方はセットで考えるべき、ということです。
Conwayの法則に関してはこちらで説明しているので、興味があればこちらを参考にしてください。
なぜこの考え方が中小企業に効くのか?
一見、大規模なIT企業だけに関係する話に思えるかもしれません。でも実は中小企業にこそ、この考え方が武器になります。
1.属人化の解消に効く
人が少ないと「〇〇さんじゃないとできない仕事」が増えがちです。
でも、業務を“サービス”のように社内で提供する形にすれば、担当者が変わってもサービスの質を維持しやすくなります。
2. 数値で見えるから改善できる
「今この部門がどれだけ忙しいのか」「どの業務にどれだけ時間がかかっているのか」
これらを可視化できれば、感覚や声の大きさではなく、データに基づいた意思決定ができます。
3. 組織の柔軟性が上がる
例えば、「社内で誰がどのサービスをどれだけ使っているか」が分かれば、人員の再配置やアウトソーシングの判断も合理的にできます。
具体例:社内業務を“サービス”にするとは?
「部門をSaaS化する」と言うと大げさに聞こえるかもしれませんが、簡単な例から始められます。
● 経理の自動申請ツール
Googleフォームで経費申請を受付け、スプレッドシートに自動記録。
→ 月末に誰が何件申請したかを一覧で把握できる。
● 営業サポートの“サービス化”
営業支援ツールを部門内で運用し、「使いやすさ」や「対応速度」を部門からフィードバック。
→ 改善の優先度が明確になる。
● SlackのヘルプデスクBot
よくある社内問い合わせをBotに集約して対応状況を可視化。
→ サポート部門の業務量が見える化され、リソース調整がしやすくなる。
まとめ:小さな組織だからこそ、“進化できる仕組み”を
中小企業にとって「変化に強い組織」を作るために、必ずしも高価なツールやフルスクラッチ開発は必要ありません。
部門を小さな“サービス”のように見立てて、利用状況を数値で測る。正しい組織の設計つまり、アーキテクチャを意識することで、組織のコミュニケーション、業務フローを常に社員と共に確認、向上できます。
人が少ない、予算が少ないという制約があるからこそ、しなやかに進化する組織づくりが、これからの中小企業には求められます。
補足:参考にした書籍 『進化的アーキテクチャ ―絶え間ない変化を支える』
『進化的アーキテクチャ ―絶え間ない変化を支える』