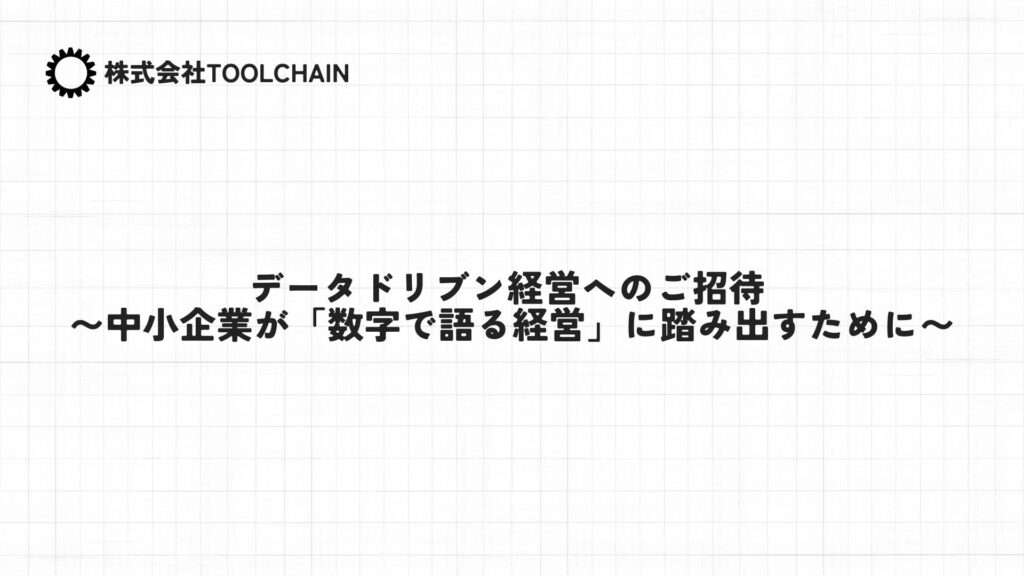
データドリブン経営へのご招待
〜中小企業が「数字で語る経営」に踏み出すために〜
創業してから過去1年間で弊社はさまざまな企業とお話をさせていただきましたが、多くの企業がいまだに「DXができていない」と言われます。
その中でよく聞く言葉があります。
「DXは余裕のある企業がやるものでしょう?」
しかし実際には、DXとは“余裕があるからやるもの”ではなく、“余裕を生み出すために行うもの”です。
IT人材の不足や、経営層自身が「データをどう活用すればよいかわからない」という構造的な課題が、
中小企業のDXを難しくしているのが現状です。
データ(数値)を使った経営とは?
弊社では、業務効率化や独自システム開発のご相談を多くいただいています。
その中で強く感じるのは、「データ(数値)を使った会話」ができないケースが多いということです。
たとえば「売上が下がっている」「忙しい」といった感覚的な議論はよくされますが、
「どの顧客層で」「どの月に」「どの商品の利益率が低下しているか」という定量的な議論に発展していないことが多くあります。
この“数値に基づく対話”ができるだけで、経営判断の精度は大きく変わります。
売上や顧客数、減価率などは経営の基本です。
また、ウェブサイトのインプレッション数やリード数は、現代のマーケティングでは不可欠な指標です。
さらに、自社が属する業界の市場規模や成長率などのマクロな視点を理解しておくことも、
経営戦略を立てる上で非常に重要です。
こうした数値に基づいて経営判断を行うことを、「データドリブン経営」と呼びます。
この記事では、まだデータ活用を始めていない企業向けに、すぐに使えるデータとツールを紹介していきます。
マクロ経済的な指標
〜外の世界を知る〜
マクロ経済とは、国や社会全体の活動を俯瞰的に捉える考え方です。
日本のGDPが世界4位になったことは記憶に新しいと思いますが、GDPもそのひとつの指標です。
経済全体のトレンドを掴むことができれば、
「どの事業に注力するか」「どの市場に営業をかけるか」といった大枠の戦略判断に役立ちます。
たとえば、自社の主要顧客層が属する業界の市場規模が縮小している場合、
早期に販路転換や新セグメント開拓を検討できます。
一方、政府が投資を強化している分野(脱炭素、生成AI、サプライチェーン強靭化など)を把握すれば、
補助金の活用や新規事業展開のチャンスをつかむこともできます。
代表的なマクロ指標・データソースは以下の通りです。
- 市場動向データ(業界全体の売上やシェア、成長率)
- 経済指標(GDP、消費者物価指数(CPI)、失業率)
- 競合分析・業界レポート(シェア動向、キャンペーン状況など)
- 社会・法規制情報(税制改正、新法導入など)
社内独自のデータ(ミクロデータ)
〜足元を可視化する〜
マクロデータが“外の世界を知るための情報”である一方、
ミクロデータは“自社の現場を改善するための情報”です。
たとえば次のようなデータは、経営に直結します。
- 売上・顧客データ日々の売上、顧客属性、購買履歴などを一元管理し、「どの商品がどの客層に売れているか」「リピーターの傾向」などを分析。
- 在庫・発注データ在庫の過不足を可視化し、製造・小売業ではコスト削減に直結。
- 生産日報・業務日報現場担当者の記録を分析し、ボトルネックや改善ポイントを特定。
- 問い合わせ・クレーム履歴顧客対応データを蓄積し、商品・サービス改善やFAQ強化に活用。
- Web/SNSアクセス・販促キャンペーンデータ集客や販売促進活動の成果を可視化。
世間で言うDXとは、実はこの“ミクロな現場データ”の活用を指すことが多いです。
つまり、派手なAI導入や高価なツールではなく、まずデータを集め、整理し、活用することがDXの第一歩です。
OSS(オープンソースソフトウェア)を利用すれば費用を抑えることもできますが、
サーバー運用や人件費が発生します。
一方、SaaSを使えば運用負担は減りますが、月額費用がかかります。
どちらを選ぶかは、自社の人材・コスト・スピードのバランスで判断すると良いでしょう。
中小企業はどうするべきか?
① 社内に運用できる人材がいる場合
社内にITスキルのある担当者がいる場合、まずは小さく始めることをおすすめします。
ExcelマクロやOSSを活用し、費用をかけずにできる改善策を試してみましょう。
特に初期段階では「見積もり作成の自動化」や「日報のデジタル化」など、
一つの業務に絞ると成果を出しやすくなります。
成果が出るまでには時間がかかるため、経営層が中長期的に活動を支援する姿勢も重要です。
分析を始める際には、DX Criteria(経済産業省)を参考に現状把握するのも有効です。
OSSを探す場合は「OSS Insight」なども便利です。
② 社内に人材がいない場合(かつ資金がある場合)
a. 外部委託する
弊社のようなIT企業に委託し、現状把握と業務効率化の戦略を二人三脚で構築する方法です。
ただし、委託任せにすると社内に知見が貯まらないため、社員育成と並行した戦略設計が必要です。
b. 社内IT部門を設立する
自社内にITチームを設け、業務改善を継続的に行う方法です。
内部に知見が貯まり、他部署展開も可能になりますが、
現在の日本ではIT人材の採用が難しい点が課題です。
データを扱う際の注意点
この記事ではデータソースも紹介しましたが、基本的には一次ソースを参照するようにしてください。
一次ソースは見づらく難しい場合もありますが、
誰かがまとめた記事を鵜呑みにすると、筆者の解釈に引っ張られる可能性があります。
経営判断は「他人の意見」ではなく「自社のデータ」と「信頼できる統計」に基づくべきです。
この一次情報を読み解く習慣をつけることで、
SNSや報道に左右されない独自の判断軸を持つことができます。
これこそが、真の意味での「データドリブン経営」の第一歩です。
最後に
データドリブン経営は、大企業だけのものではありません。
まずは「ひとつの数字を見える化する」ところから始めてみてください。
売上でも、在庫でも、アクセス数でも構いません。
その小さな一歩が、確実に“数字で語れる経営”への入り口になります。