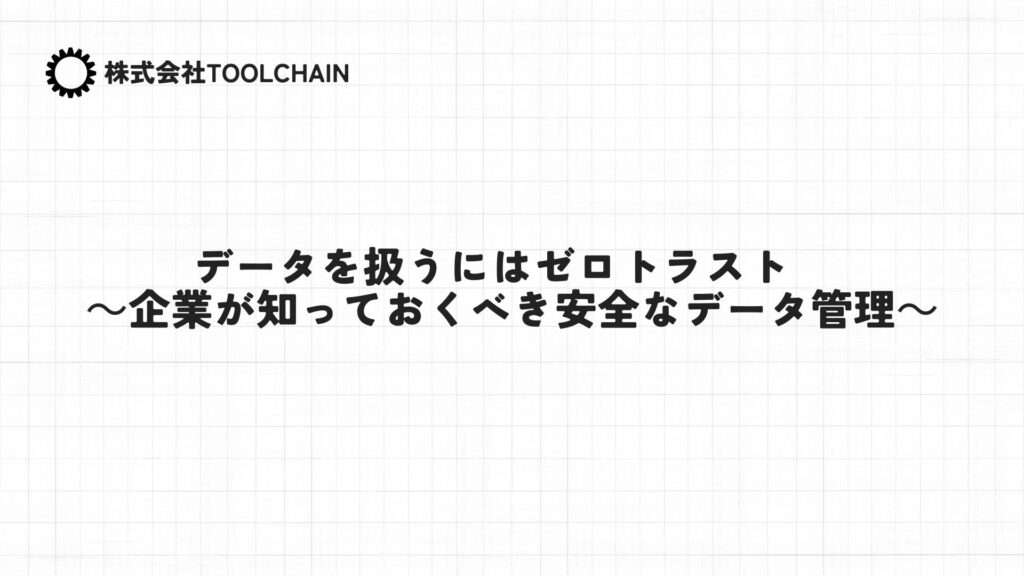
データを扱うにはゼロトラスト ~企業が知っておくべき安全なデータ管理~
現代では、社内でさまざまなデータをコンピューター上で管理したり、外部のサービスを導入することが当たり前になってきました。しかし、その一方で、IDやパスワードの管理が複雑になり、情報漏洩のリスクも高まっているのが現実です。特に中小企業では、「社内だから大丈夫」という前提で運用してしまっているケースが少なくありません。そこで注目されているのが「ゼロトラスト」という考え方です。
今回は、中小企業が実践できるゼロトラストの基本とそのステップをご紹介します。
ゼロトラストとは?
ゼロトラスト(Zero Trust)は、「誰も、何も、最初からは信用しない」という前提に基づいたセキュリティの考え方です。2009年にアメリカのセキュリティアナリスト、John Kindervagによって提唱され、次の言葉を残しています。
“Never trust, always verify.”(決して信用せず、常に検証せよ)
つまり、社内ネットワークにいるユーザーであっても、無条件に信頼するのではなく、常に検証・認証・監視を行うべきだという考え方です。
なぜ中小企業にゼロトラストが必要なのか?
中小企業では以下のようなリスクが見られます。
- 社員のパスワード使い回しによる情報漏洩
- 退職者アカウントが放置されたままアクセス可能な状態
- 社内全員が社外秘データにアクセスできる状態
これらは「信用」が前提となった運用によって発生するリスクです。
ゼロトラストの基本原則
ゼロトラストは以下の3つの原則に基づいて設計されます。
1. すべてのリソースへのアクセスは認証と認可が必要
社内ネットワークにいるという理由だけではアクセスは許可されません。ユーザーやデバイスの状態を都度確認し、アクセスを許可します。
2. 最小権限の原則(Least Privilege)
ユーザーごとに必要最低限のリソースにだけアクセスを許可します。
例:経理担当が開発サーバーにアクセスする必要はありません。
3. アクセスの継続的な監視とログ収集
一度認証されたからといって安心してはいけません。異常なアクセスがあればブロックされ、ログは常に記録・分析されます。
ゼロトラスト導入の5ステップ【中小企業向け】
中小企業でも始めやすいゼロトラストの実践ステップを紹介します。
ステップ1:IDの一元管理
Google Workspace や Microsoft Entra ID(旧Azure AD)などを使い、社員のログイン情報を一元管理します。
ステップ2:多要素認証(MFA)の導入
スマホのワンタイムパスワードなど、複数の認証要素で安全性を強化します。
ステップ3:不要なアクセス権の整理
社員ごとに必要なファイルやサービスだけにアクセス制限を設定します。
Google Workspaceなら「共有ドライブごとのアクセス権」で細かく設定可能です。
ステップ4:ログの記録と可視化
アクセス履歴や操作ログを記録・確認できるようにします。Google Workspace や Microsoft365の監査機能、ログ管理ツールの導入が有効です。
ステップ5:外部サービス連携の制御
不要な外部アプリとの連携を制限し、OAuthの認可設定も見直しましょう。
実際に起きたゼロトラスト不実施によるトラブル事例
某中小企業の例
退職者のアカウントが削除されておらず、クラウドストレージにアクセスされ、顧客情報が外部に流出。信頼の失墜と賠償責任が発生。こうした事例は決して珍しくありません。ゼロトラストを導入していれば、最小限の被害で防げた可能性が高いのです。
最後に:ゼロトラストは特別なことではない
ゼロトラストは「何か特別な大企業向けの対策」と思われがちですが、実際には中小企業にこそ必要な考え方です。特にステップ1と2は、すでにGoogleアカウントやMicrosoftアカウントを持っている企業であればすぐに導入できます。
ステップ3以降については、チームリーダーや経営者が主導し、「誰が何にアクセスできるか」を一度棚卸しすることから始めてみてください。
参考
Defining Zero Trust: Industry Approaches and Policy Frameworks for Strong Wireless Network Security